400年の時を越え、大坂冬の陣を纏いし新調だんじり見参!
まず始めに、前回このブログでお知らせした通り、岸和田だんじり祭のパレードと宮入り順が決まりまして、それにより、当サイトで開催して参りました、パレードの順番当てクイズも結果が出ました。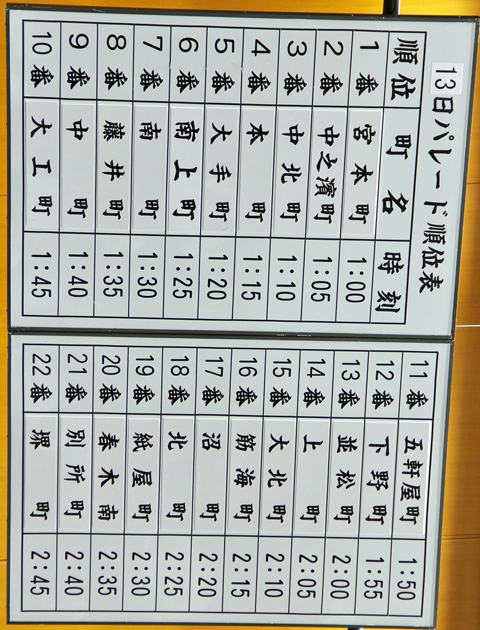
今年は残念ながら正解者ナシ!
と、ゆー訳で、クイズ応募者全員の中から厳正なる抽選のもと、当選者を決定しました。
発表は当サイトのプレゼントキャンペーンのコーナーにて掲載しています。
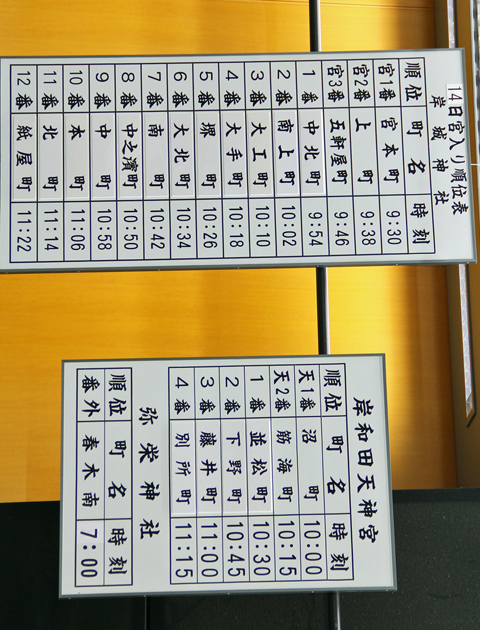
ご応募下さった皆様、ありがとうございました。
パレードの順番当てクイズは終わりましたが、まだまだプレゼントキャンペーンは続いています!
当選されなかった方にもまだまだチャンスはあります!
また、デラックス会員様には、カンカン場観覧席『本宮ラスト』のペアチケットがもう一組用意されています。
これらのプレゼントキャンペーンのご応募は明日、9月7日(日)が締切です!
まだご応募されていない方は、是非ご応募ください!
さぁ!・・・
ほんじゃブログ書こ…!
大阪は今年から来年にかけて、『大坂之陣四百年』に当たります。
1,583年(天正11年)に築城された大坂城は、豊臣家執政の拠点でありましたが、1,600年(慶長5年)の関ヶ原の合戦で徳川軍が勝利したのを機に1,603年(慶長8年)、江戸に徳川幕府が誕生し、政権は徳川家に移りました。
その後も大坂城は残されたものの、1,614年(慶長19年)の『大坂冬の陣』で、徳川軍に攻め込まれ、さらに翌年1,615年(慶長20年)、『大坂夏の陣』にてついに大坂城は落城します。
つまり、その『大坂冬の陣』から今年で400年、『大坂夏の陣』から来年で、400年の節目に当たるそうで、今年から来年にかけて、それにちなんだ様々な催事やイベントが、数多く行われます。
だんじりの分野に於いては今年、『大坂冬の陣』から題材を選んだ新調だんじりが完成され、8月31日(日)に入魂式が行われました。
そのだんじりとは…?
貝塚市・南近義地区の『堤』 のだんじりであります。

大工は岸和田の地車製作《隆匠》田中隆治棟梁、彫師は《木彫 山本》山本仲伸師と、その一門により完成しました。
こちら『堤』で昨年まで活躍した先代だんじりは、昭和14年に《絹屋》絹井楠次郎により製作されただんじりで、彫師は石田範治、石田利郎、松田正幸など。

石田範治・利郎兄弟と言えば、貝塚では現在、脇濱にある『堀』の先代だんじりや海塚のだんじりが代表的ですが、この『堤』の先代だんじりはそれよりも前の作品になります。
この先代だんじりの彫物は、腰廻りは各時代の名場面が彫り込まれていますが、見送りは『大坂冬の陣』でした。
今回新調されただんじりは、腰廻りも『太閤記』『難波戦記』に題材を求め、そして見送りは先代から引き継ぎ、『大坂冬の陣』です。
まず全体の姿見から眺めてゆくと、派手さを抑えた切妻式の破風に、寸法も大き過ぎずまとめてあります。

最初に目を引くのは正面の懸魚。

『雲海に天の逆鉾』という題材で、風になびく様を表現されています。
また『隅出す』に日本武尊や神武東征などの人物を彫り込むあたり、細かい細工で有名なな山本仲伸師の得意技が光るところかも知れません。

さて8月31日(日)、入魂式当日。
一週間前の日曜日に搬入済みということで、当日午前6時に町内を出発。

6時半頃には南近義神社に到着し、入魂式。
その後町内に戻り、お披露目曳行から遣り廻しも解禁。

窪田交差点や、地蔵堂AEON前の交差点にて遣り廻しを披露。

その後、午前10時過ぎには貝塚南小学校の校庭に曳き入れられ、見物客に展示されると、新調だんじりをじっくり見たい熱心なだんじりファンに囲まれていました。

この堤の新調だんじり完成をもって、ここ貝塚の『南近義地区』は、地区内すべてのだんじりが平成に入って新調されただんじりが揃いました。
堤の皆さん、この度は新調だんじり完成、ならびに入魂式、誠におめでとうございます!

さぁ!・・・明日はいよいよ岸和田旧市地区・春木地区の試験曳きですよ~!
| <<前の記事 | 次の記事>> |