ようやく完成! 岸和田市大工町の・・・・
ども、だん馬鹿です2週間ほど前のこと、『岸和田だんじり讀本』の著者の一人である、岸和田市大工町の萬屋誠司くんが、私が仕事場としている泉大津市内のデザイン事務所へやって来ました。
萬屋くん(通称:よろちゃん)とは、彼が岸和田だんじり会館の職員であった頃からのお付き合い。かれこれ10年以上になる。
今年新調される、大工町の地車新調委員の一人。
「やっと出来ましたわぁ~」と屈託のない笑み・・・。
「えっ!」と、驚かれた方もおられるとは思いますが、新調地車の完成は今年8月の予定。
出来上がったのは、『大正十二年新調 大工町地車記念誌』・・・・。
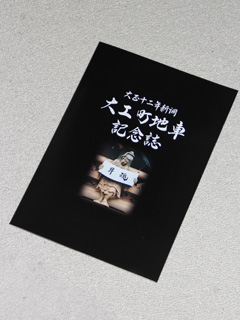
昨年の今頃から、「作るつもりしてますねん」と言っていたものが、ようやく出来上がったようである。
私も、友人の分を含め数冊お願いしていたので、2月19日(日)に受け取りに行ってきました。
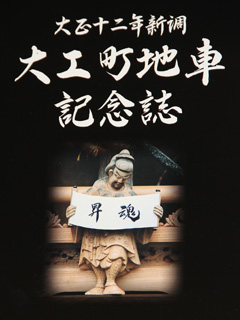
発刊されたのは、大正12年に新調された先代大工町地車の記念誌。
だんじりの記念誌と云えば、地車を新調した時、大修理をおこなった時、新調から何周年目かの時に、町内会などから発行されるもの。
特に新調記念誌は、昨今、必ず作られると云ってもいいほどで、新調記念誌収集家も数多し・・・。
しかし、新調地車の完成を前に、先代地車のものが発行されるのは、いたって稀なこと・・・・。
大正12年(1923)の新調以来、88年の長きに渡り、町の宝・町のシンボルとして曳行されてきた地車。

昨年の『岸和田祭』が、この地車での最後の祭礼。

11月3日(祝)には、昇魂式・曳き納めが盛大におこなわれました。
>>大工町の写真を見る
大工町の者としては、慣れ親しんみ、思いのたくさん詰まった地車への愛着は相当なもの・・・・。
そんな思いが、先代地車の記念誌製作へと、つき動かしたのでしょう。

この先代地車の製作にあたったのは、《朝市》こと 朝代市松 匠。
彫物責任者は、関東彫の一元林峰(かずもとりんぽう) 師。
助には、森晴秋(もりせいしゅう) 師・佐生(さしょう)武之輔 師ら。
どっしりとした、大屋根切妻型の男性的な地車で、何を隠そう、『岸和田型』地車の中でも私の好きな一台。

小屋根下の二重見送りや彫物構成などは、先々代地車(現 貝塚市名越)のものを継承。
二重見送りの上段は「本能寺」、下段には「大坂夏之陣」。
土呂幕には、『難波戦記』で活躍した豊臣方の武将 薄田隼人・荒川熊蔵・後藤又兵衛の勇姿が、三方に散りばめられている。
これも、先人から受け継いできた大工町の地車への思い入れの表れなのでしょうか・・・・?
この地車は、堺市美福連合 大庭寺へ売却され、現在、堺市草部の《小松工務店》小松宏行 匠の元で修理中。
今年4月29日(日)には、この地車を譲り受けた大庭寺の地で、装いも新たに入魂式・お披露目曳行がおこなわれることでしょう。
なお、大工町の新調地車は、今年8月19日(日)の入魂式・お披露目曳行に向け、地元大工町に居を構える《池内工務店》池内幸一 匠の元で製作中。
彫物は、《木彫山本》山本仲伸 師が担当。
先代地車を踏まえ、数々の創意工夫を凝らし製作しているとは聞いていますが、どのような地車が出来上がるのか、今から晴れの日が待ち遠しい限りです・・・・。
| <<前の記事 | 次の記事>> |