住之江區だんじりの修復を追い求めて…
前回のつづきです。神戸市東灘区・住之江區のだんじりが、泉佐野市にある板谷工務店にて修復されるにあたり、先日11月1日(土)に、その解体作業をちょいとばかり見学させてもらいに行きました。

前回のブログでは、解体作業を見守りながら、このだんじりの歴史を紐解いてみました。
その中でひとつ訂正しておかなければならないのは、このだんじりを新調した『高羽』を、『東灘区』と表記しましたが、正しくは現在の『灘区』でした。
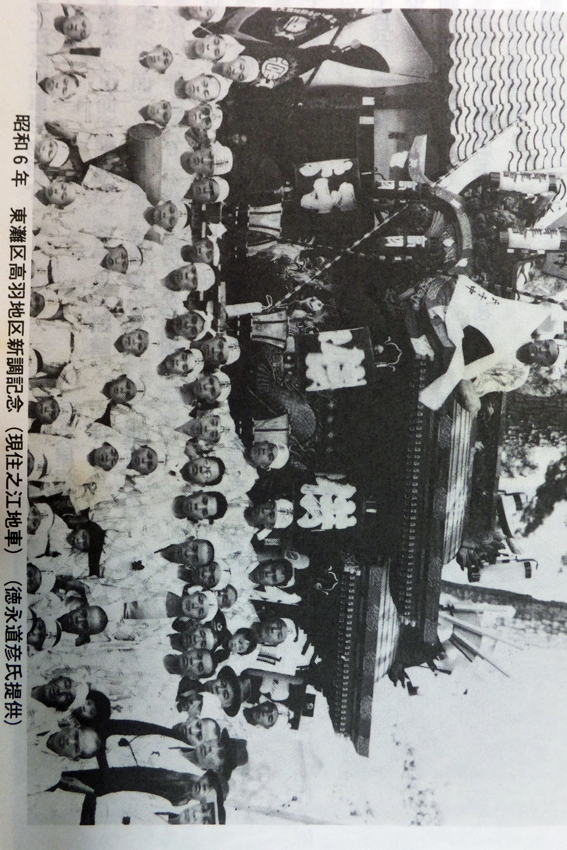
謹んで訂正・・・
さて今回は、解体作業の中でバラバラになった、各彫物を一部ですが鑑賞してみたいと思います。
まずはやっぱり『獅噛み』!

だんじりの『顔』ですわ。
空襲によって屋根廻りに大きな被害を受けた後、昭和25年の完成に向けて川原啓秀が再度彫り直したという作品。

現在、屋根廻りの彫物はおおかた昭和25年までに彫り直されたものであります。
大屋根正面懸魚『飛龍』

こちらの小屋根正面懸魚『鷲』は、大屋根正面よりも、いっそう川原啓秀の色が出ている作品ですね。

大屋根左右の枡合。

だんじりの枡合と言うよりは、太鼓台の『狭間』に近い組み方かも知れません。

今回、大屋根を取り外す際、先に枡合を取り外したのは、この枡合が枡組に組み込まれておらず、大屋根を浮かすと枡合が外れて落ちてしまうからだったと思われます。

大屋根正面の車板は、大屋根に組み込まれたまま取り外されてあるので、見ることは叶いません。
こちらは大屋根後ろの車板。

だんじりによっては『欄間』『間仕切り』などの呼び方もしますが、ちゃんと屋根の棟の懐に組み込まれる形になっているので、『車板』の呼び名がふさわしいでしょう。
鯉の滝登りです。
これなんか、今回ワタクシが一番『おっ!』って思った作品なのです。

と言うのも、この部分はだんじりの内側なので、普段の祭礼でも見ることが出来ません。
そして今回初めてお目にかかれたこの部材の彫物が、『これこそ井波彫刻や!』と言えるような彫物だったので、よけい『おっ!』って思ってしまったのですよ!
井波彫刻によくある『レリーフ』のような雰囲気の彫り方に、鯉の滝登りの題材と言うことで、ワタクシの目はちょっと釘付けになりました。
こちらは脇障子、『獅子の子落とし』で、左右対称に彫られてあるのですが・・・


図柄は、富山県は井波彫刻の総本山である『瑞泉寺』にある、勅使門の『獅子の子落とし』によく似ています。

おそらくそれを参考に彫られたのではないかと思われ、故郷である井波を離れ、神戸でノミを振るっていた川原啓秀の、望郷の思いも込められているかのような作品で、これもちょっと感慨深い作品ですね。
こうして見てくると、名匠・川原啓秀が『井波彫刻』の誇りを胸に、その技法を如何なく発揮して彫り込まれたものであることが伝わってきます。

今回の修復は、主に締め直しが目的なので、大きな部材の新調も洗いもなく、彫物のやり替えもありません。

この黒々とした色のまま、原寸で組み上げられて戻ってきます。
住之江區の名地車、来年には再び激しい祭を見せてくれる事でしょう。
では今回はこの辺で~!
| <<前の記事 | 次の記事>> |